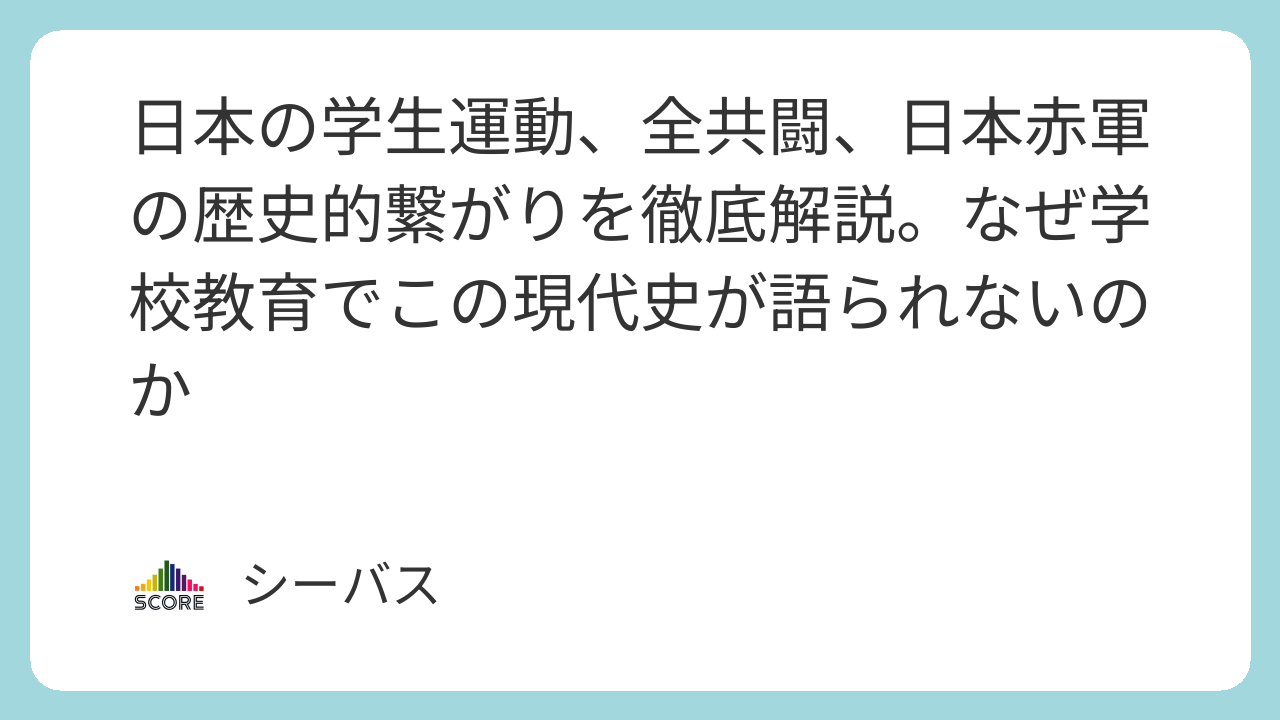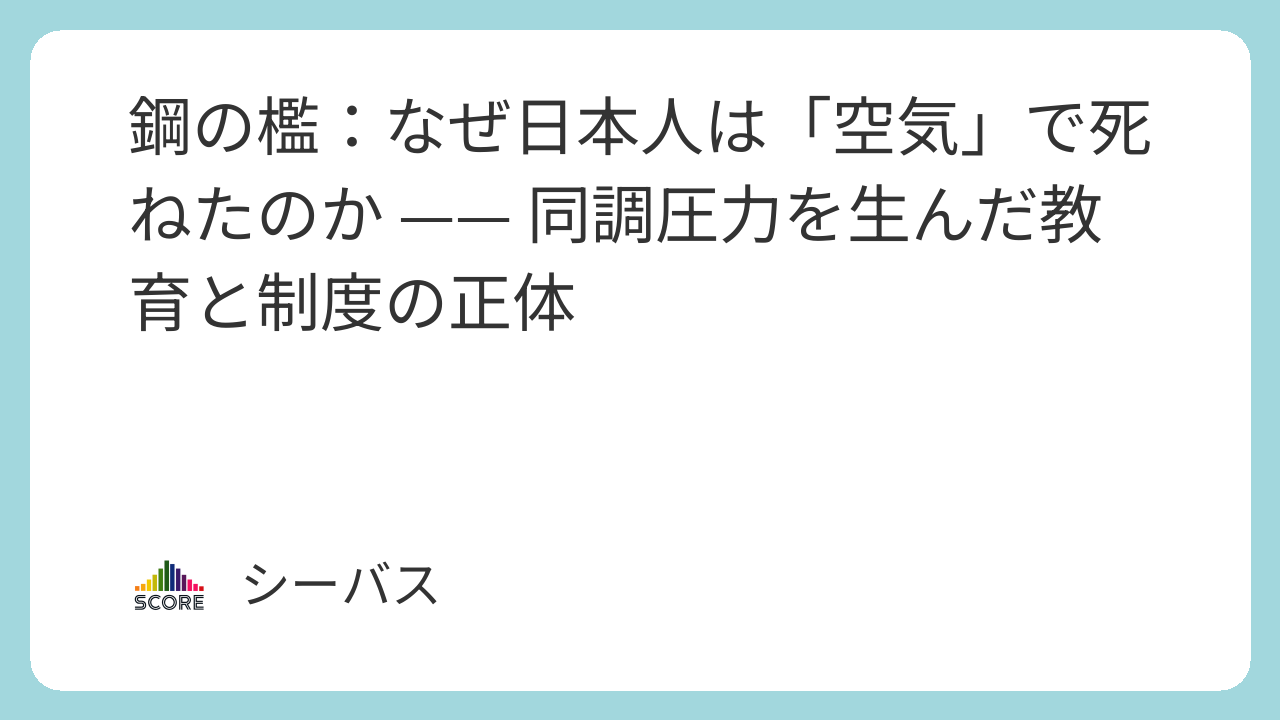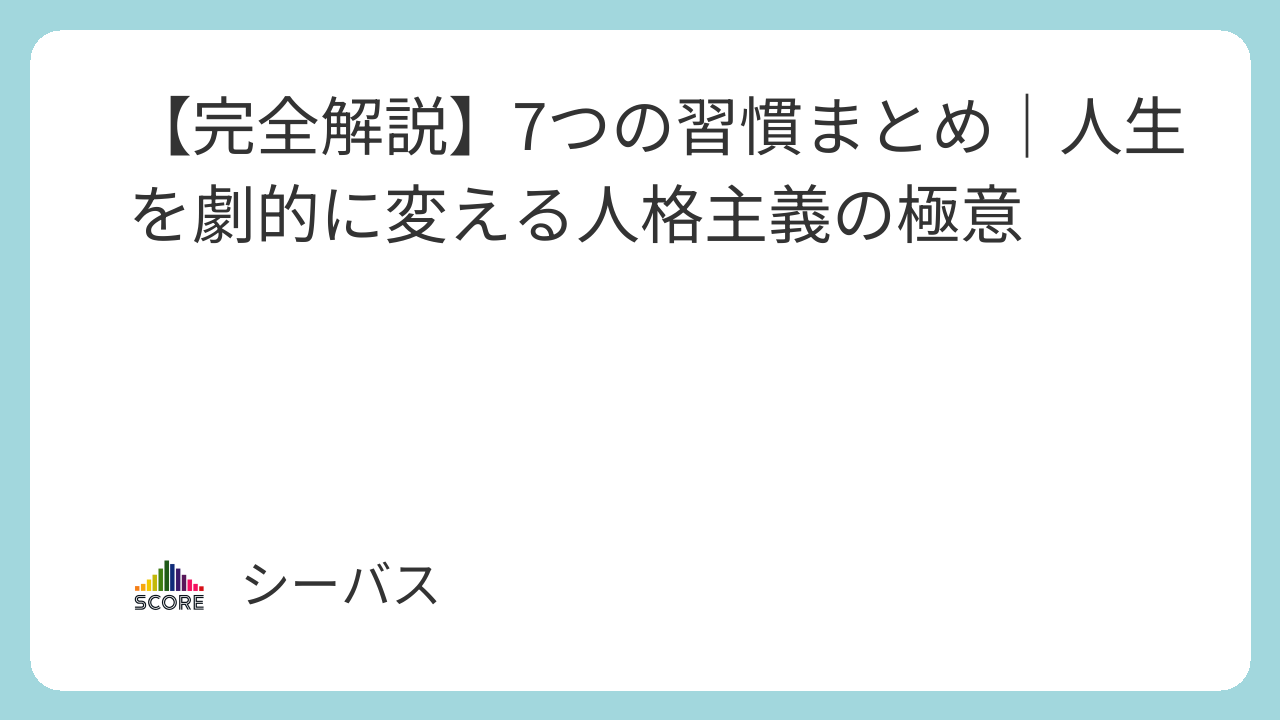学校が教えない空白の戦後史:全共闘から日本赤軍へ、若者たちが夢見た「革命」の光と影
「全共闘(ぜんきょうとう)」「日本赤軍(にほんせきぐん)」……。こうした言葉を聞いて、あなたは何を思い浮かべるでしょうか?「昔の過激な人たち」「なんだか怖いテロリスト」「今の日本には関係のない過去の話」。おそらく、そんなイメージが一般的かもしれません。
実は、この1960年代後半から70年代にかけての激動の時代は、現在の日本の政治的無関心や、社会の「空気」を形作った決定的な分岐点でした。しかし、驚くべきことに、これほど重要な歴史を私たちは学校でほとんど教わりません。なぜ、教科書はこの時代を「空白」にするのでしょうか。全共闘と日本赤軍にはどのような繋がりがあったのでしょうか。
1. 繋がりと変遷:大衆運動が「テロ」に変わるまで
まず整理しておきたいのは、これらが独立した出来事ではなく、一つの地続きのストーリーであるということです。この歴史は、大きく「大衆的な盛り上がり」から「少数精鋭の過激化」へと濃縮されていく過程として捉えることができます。
1960年代:全共闘の誕生(大衆的な熱狂)
始まりは、各大学で自然発生的に起きた学園紛争でした。学費値上げ反対や大学運営への不満をきっかけに、「全学共闘会議(全共闘)」が結成されます。これは特定の政治組織(セクト)に属さない「ノンセクト・ラジカル」と呼ばれる無党派の学生をも巻き込んだ、巨大なうねりでした。
当時の大学生の多くがヘルメットを被り、バリケードの中に身を置きました。東大紛争での「安田講堂占拠」などはその象徴です。この時点では、まだ運動には「自分たちの手で大学を、そして社会を変えられる」というポジティブな熱気が満ち溢れていました。
1969年:赤軍派の結成(純粋ゆえの過激化)
しかし、警察の制圧が進み、安田講堂が陥落すると、大衆運動としての全共闘は行き詰まりを見せます。「デモだけでは世界は変わらない」——そう焦燥感を募らせた一部の過激な若者たちが、共産主義者同盟(ブント)から分派し、赤軍派を結成します。彼らのスローガンは「武装蜂起」でした。
1970年代:二つの「赤軍」と悲劇的な結末
ここから運動は、一般市民の感覚から完全に乖離した「狂気」へと突き進みます。赤軍派は、弾圧を逃れるために二つの道を選びました。
- 国内組(連合赤軍): 国内で武装闘争を継続しようとしたグループ。しかし、彼らが歴史に残したのは革命ではなく、仲間内での凄惨なリンチ殺人(山岳ベース事件)と、日本中がテレビに釘付けになった「あさま山荘事件」でした。
- 海外組(日本赤軍): 重信房子らがパレスチナへ渡り結成。中東の武装勢力と手を組み、「テルアビブ空港乱射事件」などの国際テロを引き起こしました。
2. なぜ彼らは「革命」にのめり込んだのか?
現代の私たちが最も理解に苦しむのは、「なぜエリート学生たちが、あれほどまでに暴力的になれたのか」という点でしょう。彼らを突き動かしていたのは、単なる若気の至りではない、当時の時代が抱えていた深い矛盾でした。
嘘っぱちの「平和」への嫌悪
1960年代、日本は高度経済成長を遂げ、表面上は平和を享受していました。しかし、すぐ隣のベトナムでは戦争が激化し、日本の米軍基地から爆撃機が飛び立っていました。若者たちの潔癖な正義感は、「平和憲法を掲げながら、アメリカの戦争に加担して繁栄を謳歌している。この国は嘘をついている」という欺瞞(ぎまん)を許すことができませんでした。
「管理社会」への反抗
当時の大学は、企業に「従順な会社員」を送り出すための工場のような場所になりつつありました。「俺たちは、システムの歯車になるために生まれてきたんじゃない」という主体性の回復を求めた若者たちのエネルギーが、皮肉にも「組織への絶対服従」を求めるカルト的な過激化へと繋がってしまったのです。
3. なぜ教育現場はこの事実を「隠す」のか?
教育現場や文部科学省の根底には、若者の政治的エネルギーを制御不能にさせたくないという、一種の防御本能があると考えられます。
成功物語という「正史」を守るため
学校の日本史は、戦後を「焼け野原からの奇跡の復興」という物語で描きがちです。ここに学生運動を挿入すると、「国民が一丸となって頑張った」という物語が崩れてしまいます。若者が国を否定し、社会を破壊しようとした事実は、教育上の「不都合な真実」なのです。
政治的中立性と「事なかれ主義」
学生運動の当事者の多くは存命であり、現在は社会の要職に就いています。また、この運動を「理想主義」と見るか「テロ」と見るか、いまだに政治的な評価が分かれています。教員は政治的にデリケートな問題を扱うことを極端に避けます。「教えないことが一番安全」という結論に至ってしまうのです。
「直接行動」を学ばせたくない思惑
不満があるならデモをしろ、バリケードを築けと教えるわけにはいきません。学生運動の手法を教えることは、教育そのものが依って立つ「秩序」への反抗を肯定することになりかねない——。そんな当局の恐れが、この歴史を隅へと追いやっていると言えるでしょう。
4. 挫折した若者たちの「その後」
「あんなに暴れていた学生たちは、どこへ消えたのか?」答えは簡単です。彼らの多くは、ある日突然髪を切り、スーツを着て、かつて否定していた「大企業」の中へと消えていきました。
坂本龍一、村上春樹、加藤登紀子といった著名人は、その熱狂を芸術へと昇華させましたが、名もなき数万人の元活動家たちは、その挫折と「恥」を胸に秘めたまま、猛烈に働き始めました。日本の80年代のバブル経済を支えたのは、実は「革命に失敗した若者たち」だったという皮肉な現実があります。
5. 現代に続く「空白」の影響
1972年の連合赤軍事件は、当時の国民に「政治に関わりすぎると、最終的には仲間を殺すような悲惨な結末になる」というトラウマを植え付けました。それ以来、日本では「政治について熱く語ること」がタブー視され、若者の政治的無関心が加速しました。教育がこの歴史を放置してきたせいで、私たちは「なぜ今の日本がこれほどまでに静かなのか」という理由さえ、知る機会を奪われているのです。
結びに:歴史を「知る」ということ
かつての学生運動や日本赤軍の行動を、今の価値観で「正義だった」と肯定することは難しいでしょう。しかし、教育がこの事実を隠し続けることは、それ以上に危ういことではないでしょうか。若者が何に絶望し、何を信じ、なぜ失敗したのか。そのプロセスを学ぶことは、現代の閉塞感を打ち破るヒントを見つけるためにも必要不可欠です。